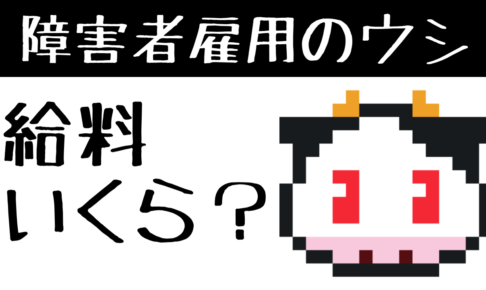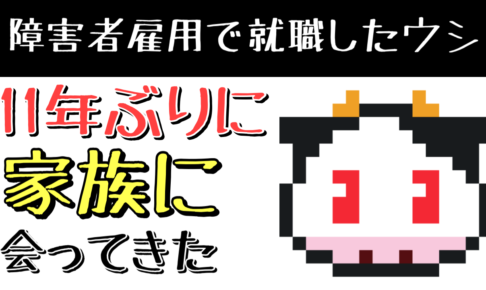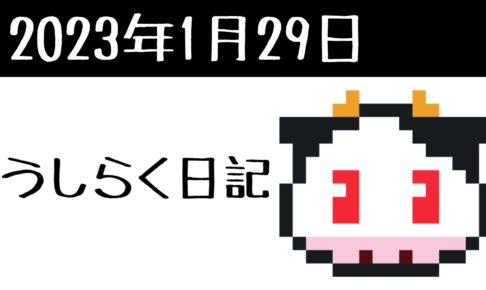うしらくです、どうも!

と、思ったことはありませんか?
断捨離やミニマリストな生活が当たり前になった現代ですが、家電を捨てるのは中々勇気がいりますよね。
そんなあなたに、ぼくの断捨離体験談をお届けします。
ぼくは約2ヶ月前に、4つの家電を断捨離しました。
- 洗濯機
- 掃除機
- 炊飯器
- 電子レンジ
日常生活で必須な家電たちですが、あえて捨ててみたんです。
で、この記事では
- 家電を断捨離したらスッキリするのか?
- ストレス解消法として、断捨離はアリ?
- 家電を捨てて、不便な生活にならないのか?
について、お伝えします。
あなたの断捨離ライフを、後押しできたら幸いです。
結論:家電の断捨離で、豊かな時間が手に入った
はい、いきなり結論です。
ぼくは、家電を断捨離することで、豊かな時間を手に入れました。
なぜ、そう感じるのか?
それは、「時短生活」ほど、人間のライフスタイルを圧迫しているからです。
時短・効率化するほどにやることが増え、心理的プレッシャーも増える
大正から昭和、平成から令和と、時代が進むにつれ、家電製品の進化は劇的に進みました。
もともと、大正時代から昭和中期までは、各家庭に電化製品は普及していませんでしたからね。
例えば、洗濯機についていうと、明治~昭和中期までは「洗濯板」で衣類を洗っていました。
洗濯板(センタクイタ)
明治時代に外国から入ってきたもので、洗濯機が登場するまで使われました。
洗濯板を使う前は、手でもんだりして洗ったりしました。
引用元:金沢くらしの博物館
また、洗濯機が誕生してすぐは「高級品」だったため、購入できたのは、ほんの一握りの家庭だけだったようです。
昭和5年(1930)に第1号が誕生していますが、かなり高級品だったので、ふつうの人は買えませんでした。
昭和20年代になるといろいろな洗濯機が作られるようになりました。
引用元:金沢くらしの博物館
つまり、人間はもともとは「電化製品がなくても生きていける」生き物だったんです。
経済が発展し働き方が多様化したことで、電化製品が普及した
しかし、昭和に入り、高度経済成長やバブル時代、人々のワークスタイルの変化により、電化製品が爆発的に普及していきました。
1960年代になると高度成長に伴う所得の増加は、家電の普及率を高めた。
また、家電の普及は、家庭での消費電力を増加させた。
1966年、日本初の商業用原子力発電所が東海発電所で稼働する。
引用元:年代流行
なくても生きていけるものを「ないと生きていけない」と思わされている
ぼくが生まれたのは、1985年(昭和60年)。
生まれた直後から、わが家には「当たり前」のように電化製品がありました。
なので、自分が大人になって一人暮らしを始めたときも、
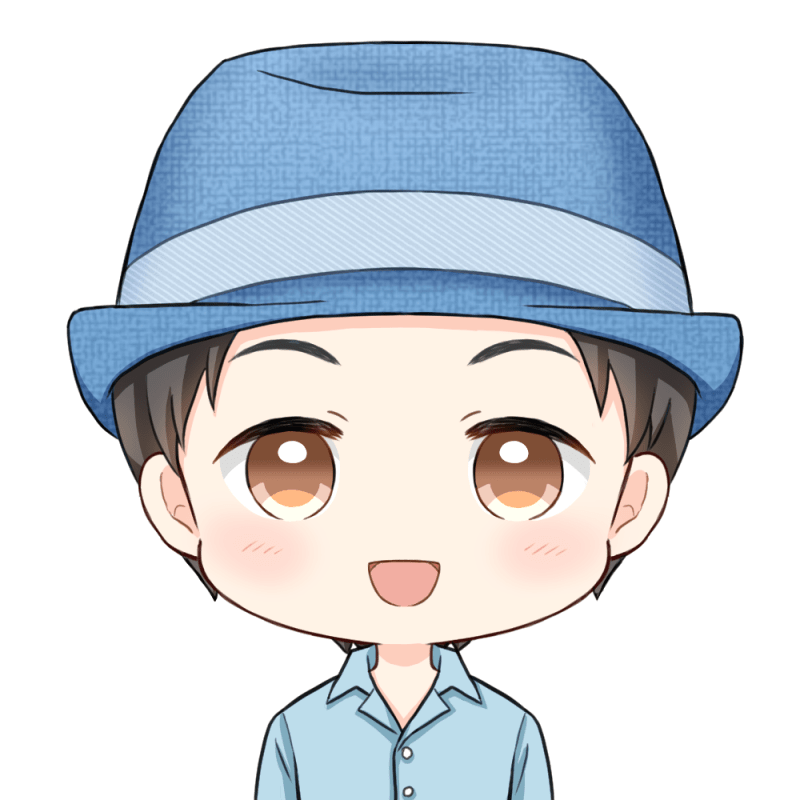
と思い、16万円分の家電製品を購入しました。
時短をするための道具に、時間を奪われていた
で、家電製品ってのは、人間の生活を楽にするためにあるわけですね。
- 洗濯する手間を、洗濯機で省く
- 掃除する手間を、掃除機で省く
- ものを温める手間を、電子レンジで効率化する
- 米を炊く時間を、炊飯器で節約する
など、今でいうところの「アウトソーシング」を電化製品にしていたわけです。
では、そうやって浮いた時間を、あなたは何に使っているでしょうか?
時短で浮いた時間の使いみちは、ほぼ無駄な時間に浪費している
例えば、洗濯を全自動洗濯機に任せることで、30分~1時間くらい時間が浮いたとしましょう。
その浮いた時間を、何に使っているでしょうか?
- ネットサーフィン
- SNSやスマホゲーム
- 他の仕事をギュウギュウに詰める
- 他の家事を同時並行でやる
人によって時間の使い方は違うけれど、それらの時間は本当に必要なのか?
浮いた時間に、無理やり別の予定を詰め込むことで、余計に忙しくなっていませんか?
効率的に仕事や家事をこなすことは、たしかに大切です。
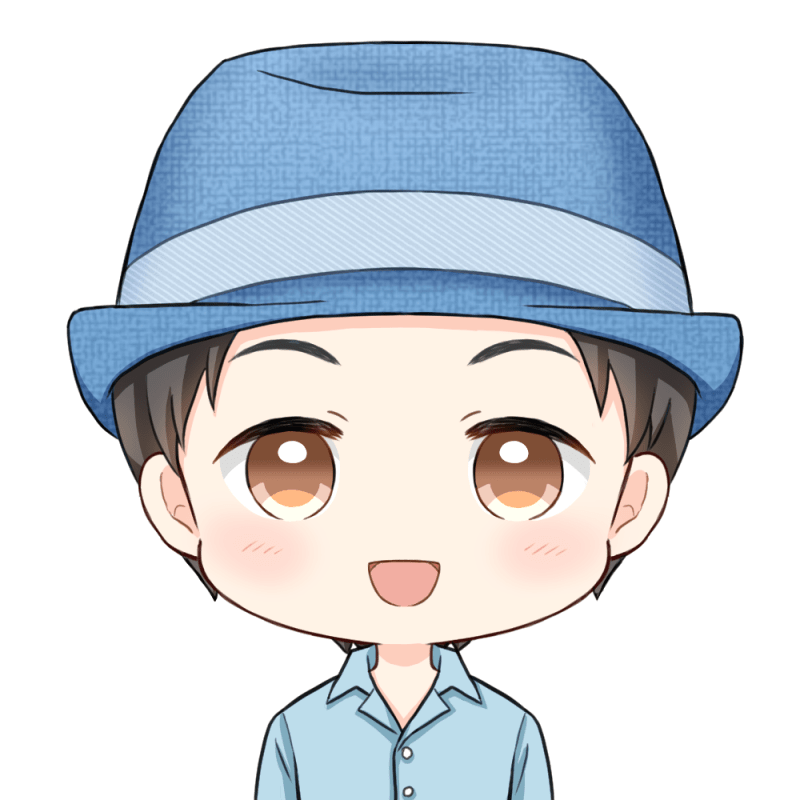
ぼくは、時短することで逆に時間に「追われてる」感覚を感じたので、時短生活をやめることにしました。
結果、家電を捨てて2ヶ月近くたった今、ゆとりのある毎日を過ごせています。
家電を断捨離して、アナログで「代用」する方法
では、ここからは、ぼくが家電を捨て、アナログ生活で「代用」している方法を紹介します。
- 炊飯
- 掃除
- 洗濯
- 電子レンジ
の順に、紹介していきますね。
炊飯器を捨て、土鍋でごはんを炊く
まず、炊飯から。
炊飯器を捨て、土鍋でごはんを炊いています。
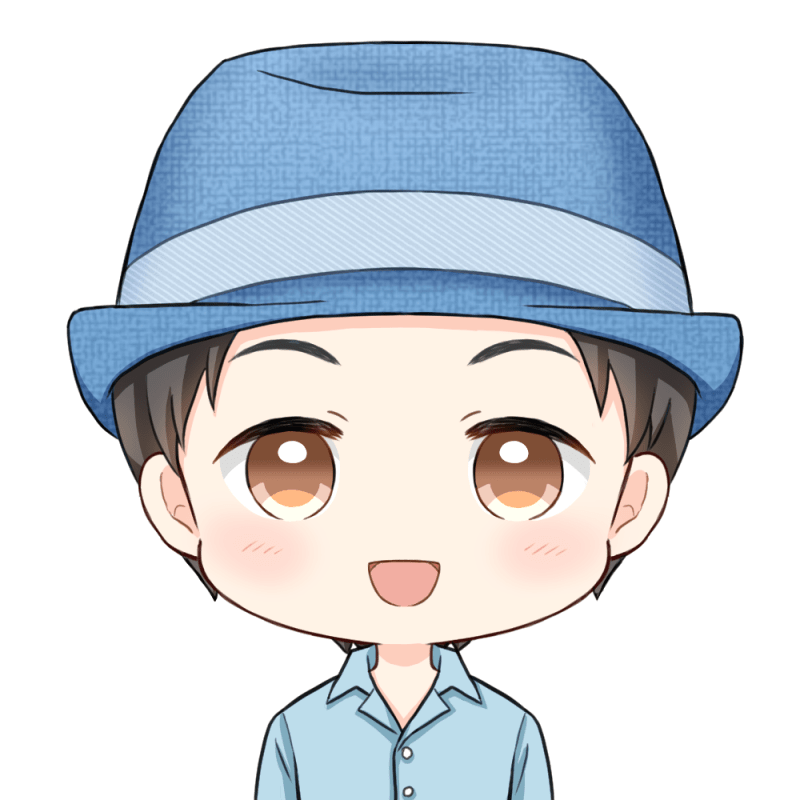
でも、うまくご飯が炊けたときはめっちゃ美味しいし、達成感があります。
上手にご飯を炊くために、30分近く土鍋につきっきりなので、その時間は一見すると無駄です。
しかし、そういう無駄な時間ほど、ぼくは「安心」を感じますね。
掃除機を捨て、毎日ワイパーがけしている
うちはフローリングなので、毎日ワイパーがけをしています。
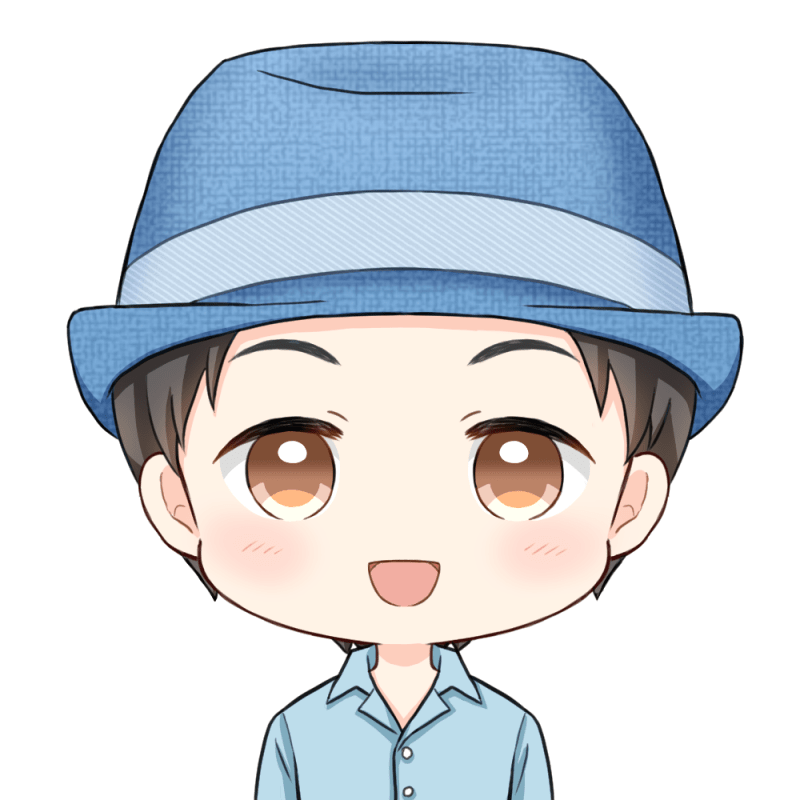
こちらのワイパーは別売りの「ドライシート」を買っているのですが、一袋あたり30枚入で100円。
一日あたり約3円と、低コストで済みます。電気代も節約できるし、お得!
また、ドライシートを使って、机やエアコンの上、トイレや風呂場なども拭き掃除しています。
毎日掃除していると「そもそも汚れない」ので、掃除機を捨ててからの方が、部屋中がきれいになりました。
洗濯機を捨て、バケツで手洗いをしている
一番大変なのが、洗濯です。
ぼくはバケツを使って、手洗いで洗濯をしています。
- バケツにお湯をはり、洗剤を溶かす
- 衣類をバケツに入れ、30分間つけおき
- バケツのお湯を捨て、3回すすぐ
- バケツに柔軟剤を溶かした水を入れ、5分つけおき
- 衣類を手で絞って、脱水して干す
という流れで、毎日洗濯してますね。
洗濯物を溜めると脱水で絞るのが大変なので、毎日こまめにやるのを心がけています。
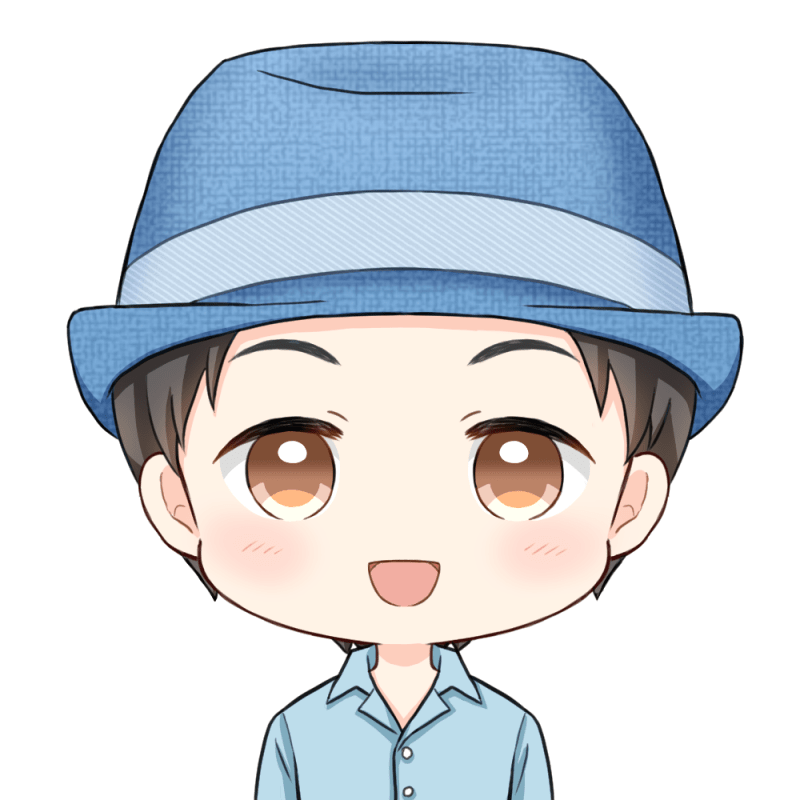
電子レンジはなくても大丈夫
最後に、電子レンジです。
電子レンジは、なくても生活に支障はないですね。
- 弁当はコンビニやスーパーで温めればいい
- 食材の解凍は、自然解凍でいい
- 電子レンジ調理の冷凍食品は、買わなくていい
とまぁ、わざわざ電子レンジで温めるものって、ほぼ無いんですよね。
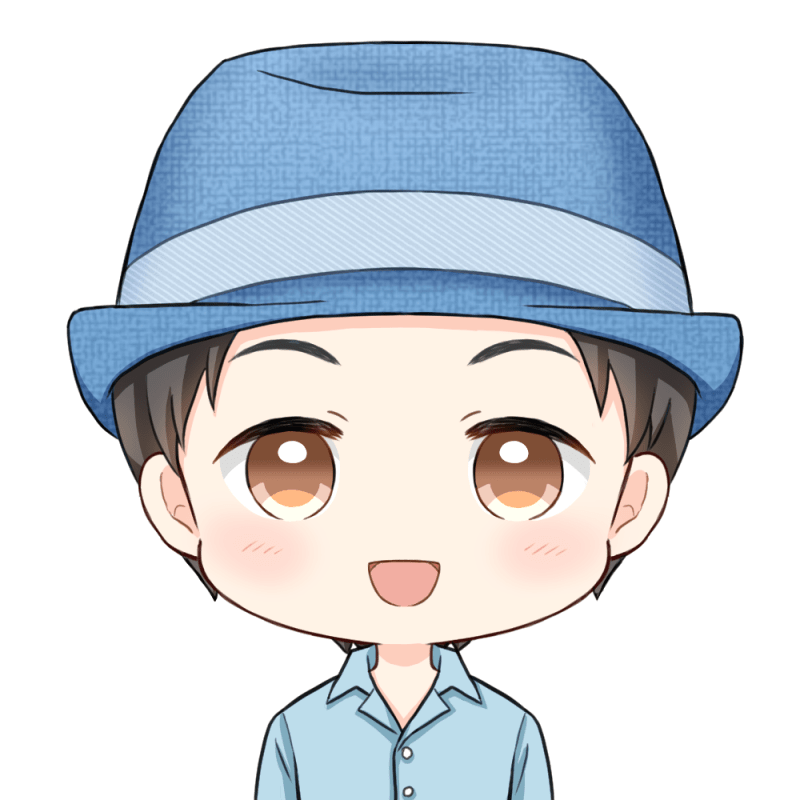
断捨離を通して、「電気のない生活」でも生きていけるようにする
自然災害が多発している昨今、長期的に停電して「電気のない生活」に襲われることもあります。
台風15号の影響による千葉県の大規模停電で、14日も約14万3100戸(午後10時現在)で停電が続いている。
この24時間で3万戸超が復旧したものの、大量の倒木に阻まれるなどして復旧作業は依然として難航している。
引用元:毎日新聞
こういう事態に遭遇したとき、「電化製品に依存した生活」に慣れてしまっていた場合、家事がなにも出来なくなってしまいます。
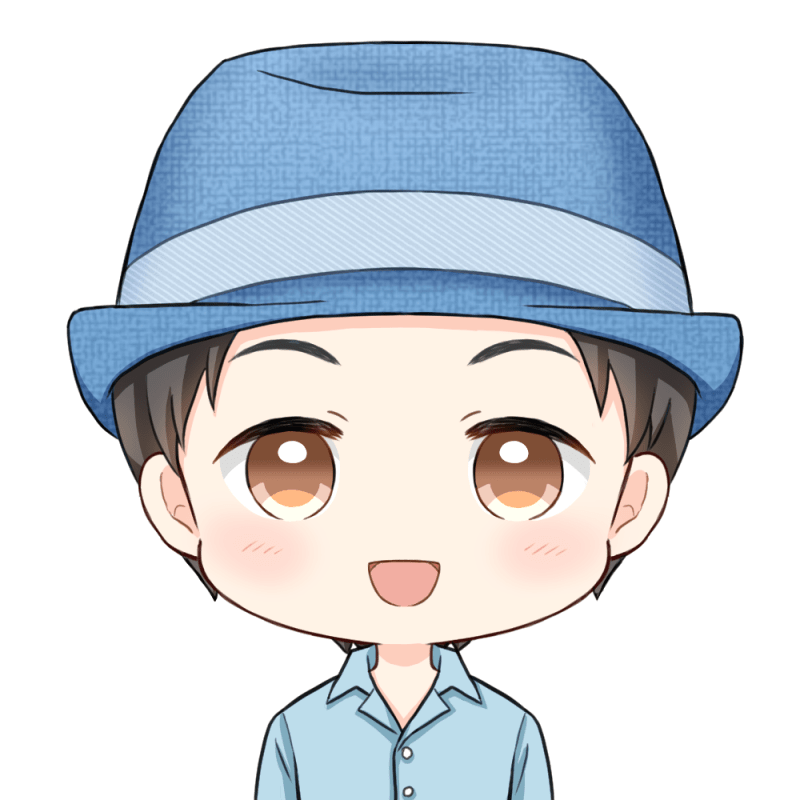
でも、普段からアナログな生活をしていると、わりと対処しやすいと思うんですよね。
少なくとも、ぼくは
- 炊飯
- 掃除
- 洗濯
については、電気がなくても普通にできます。
なので、長期的に停電したとしても、わりと適応できるはずです。
「もしもの事態」に直面したときでも、「自分の身一つ」で生活できるようにしておくと、メンタル的な負担は少なくなるでしょう。
うしらく的まとめ
今回は、家電の断捨離について紹介しました。
家電の断捨離は、ストレス解消だけでなく、災害時にも強く生きるために有効です。
まぁ、いきなり全ての家電を捨てるのは極論すぎるのでオススメしないけど、今あなたが迷っているならば、どれか一つを捨ててみてはどうでしょうか?
捨ててみると、意外と「なくても大丈夫じゃん!」と思えるかもですよ。